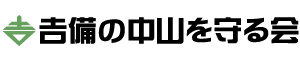吉備津神社
平安時代から明治までは「吉備津宮」。明治以降は「吉備津神社」。主神は吉備津彦命。歴史における初見は『続日本後紀』で承和14(847)年。延喜式神名帳(927年)には名神大社「吉備津彦神社」として掲載。天慶3(940)年に一品という最高位を受け「一品吉備津宮」と呼ばれた。平安時代後期諸国に一宮ができると、備前・備中・備後の三国の一宮(三備の一宮)と称された。比翼入母屋造(吉備津造り)と呼ばれる本殿と拝殿は、室町時代の再建で国宝。本殿には吉備津彦命、相殿に夜麻登登母母曾毘売命、若日子建吉備津日子命など、艮(北東)の隅には温羅が祀られている。本殿の真後ろに扉があり背後の飯山を拝んでいたという研究者もいる。南随身門、北随身門、御釜殿は、国の重要文化財。長い廻廊(389m)は岡山県の重要文化財。特殊神事は年末の御煤払、七十五膳据。鳴釜神事は有名。Tel(086)287-4111